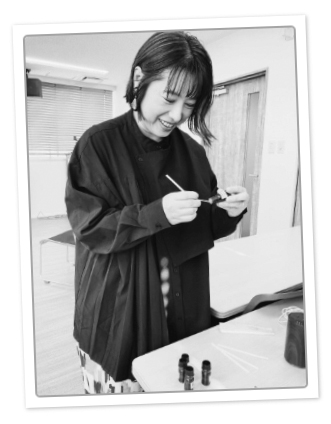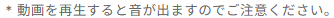
こんにちは。モノコスメラボのサイガです。
「精油ってよく聞くけど、実際にはどんなもの?」「アロマに興味はあるけど難しそう…」
そんな風に感じている方に向けて、精油の基礎から簡単な使い方まで、やさしく解説します。
香りの力を味方にすれば、日々の暮らしがもっと心地よくなるはず。まずは第一歩、精油の世界をのぞいてみましょう。
精油って何?基礎から学ぶアロマの世界

▮植物が生きていくために自ら作る物質が精油
精油は植物の中の「分泌腺」という部分でつくられ、「油胞」として蓄えられているものです。植物は、花、葉、果実の皮、樹皮、根茎など、様々な部位から香りを放ちますが、その香りのする部位に精油は蓄えられています。その精油が蓄えられた部位を中心に収穫し、それぞれ植物の特性に合わせて「水蒸気蒸留法」「圧搾法」「溶剤抽出法」「アンフルラージュ法」などの特別な方法で精油は抽出されます。
(引用:アネルズあづさ著(2023).アロマ図鑑.ナツメ社)
植物が生殖活動を行うためにも、精油は重要な役割をもっていて、例えば自ら動けない植物がいい香りでミツバチをはじめとするポリネーター(花粉媒介者)と呼ばれる様々な虫たちを引き寄せて受粉のサポートをしてもらったりしています。また、植物自身を害するものから香りで寄せ付けないようにして身を守ったり、生きていくために必要不可欠な物質なのです。
そんな貴重な精油を人間は使わせてもらっているんだなぁ、大事に使わないとなぁと常々思います。
▮アロマオイルとの違いは?
「アロマオイル」という言葉もよく耳にしますが、実は精油とは少し異なります。
アロマオイルには、人工香料やキャリアオイルが混ざっているものも多く、**100%天然成分のものだけが「精油(エッセンシャルオイル)」**と呼ばれます。(アロマ=香りなので、香りがあるオイルはアロマオイルとなるイメージです。)
購入時には、学名やラベル、成分表示をしっかり確認しましょう。
合成香料やアルコール、キャリアオイルが悪いというわけではなく、アロマオイルをエッセンシャルオイルとして販売しているものは悪質なので、そこのところを理解しておくのは大事だと思います。
▮精油はどうやって作られているの?
精油は、主に「水蒸気蒸留法」や「圧搾法」で抽出されます。
例えば、ラベンダーは水蒸気蒸留法で精油が集められます。オレンジやレモンのような柑橘系は果皮を押しつぶして抽出する圧搾法で抽出されます。(柑橘系は光毒性成分を含まないようにするために水蒸気蒸留法で抽出されることもあります。ただし、香りに少し違いがあり、圧搾法の方がフレッシュでみずみずしい香りがします。)
ジャスミンは溶剤抽出法(アブソリュート)と呼ばれる方法で抽出されます。溶剤抽出法では、植物の花弁や繊細な部分を傷つけずに香り成分を取り出すことができます。ジャスミンの花は特にデリケートで、他の方法だと香りが損なわれやすいため、この方法が適しています。アンフルラージュ法は、花を動物性脂肪に置いて香りを吸収させる古典的な方法で、特に高価で珍しい香りの抽出に使われます。これらの精油生成法は植物の特性に応じて選ばれ、それぞれの香りを最大限に生かすための工夫がされています。
精油は大量の植物からほんの少ししか取れない、貴重な油溶性成分なんです。
余談ですがアンフルラージュ法と聞くと、昔観て衝撃的だった映画「パフューム ある人殺しの物語」をフラッシュバックさせるのでちょっとドキドキします。
合成香料との違いとは?

▮成分の違い:天然 vs 人工(化学合成)
天然香料(精油)は植物の一部から抽出された植物自らが作り出した100%天然成分で構成されています。
合成香料は化学的に合成された香気成分です。
合成香料は、天然には存在しない香りを作ることができたり、安定性やコストの面でもメリットがあります。安価で大量生産が可能なため、香水や柔軟剤、消臭剤などに多く使用されています。
例えば、柑橘系にも含まれる「リモネン」という成分ですが、レモンっぽい香りがする成分で合成香料や洗剤、プラモデル用接着剤などに使われています。
▮香りの深さと変化
天然の精油は、単体の精油(シングルノート)でもたくさんの芳香成分がそもそも含まれているので単体の合成香料では得られない奥行きと変化を持ち合わせており、香りの持続時間や香り方が異なるのも特徴です。
単体の精油各種でもその精油ごとに揮発する時間に差があり、その時間を「ノート」という言葉で表し、ARTQオーガニクスの精油では香りの特性、成分の特性と揮発性から5種類のノートに分類されています。
トップノート/トップ・ミドルノート/ミドルノート/ミドル・ベースノート/ベースノートです。
もちろん合成香料も、たくさんの香りの成分を調香師さんが組み合わせることで、奥行きや変化のあるフレグランスが生まれ、人の魅力を香りで引き立てる魅力的なアイテムになります。
香水でも香る時間によってトップノート/ミドルノート/ラストノート(ベースノート)と呼び、香調別にフローラルノートやシトラスノート、ウッディノートなどと表現したりします。
現在、合成香料の種類は3,000~4,000種類ほどあるといわれており、精油は一般的に流通や利用されているものは300~400種類といわれています。
何千種類にも及ぶ香料や天然香料(精油)をブレンドして香水や化粧品に使われる香料が作られると思うと本当に調香師さんはすごいなぁとただただ尊敬しかありません。
▮心や体への影響
精油には心や体に働きかける力がありますが、まだ分析されていない成分も多く含まれており、どの成分がどのように作用しているのか、はっきりわかっていない部分もたくさんあります。これが精油の魅力であり、私たちが日常に取り入れたいと感じる理由のひとつです。
合成香料は強い香りが長時間持続する反面、人によっては頭痛やアレルギー反応を起こすこともあります。香害(こうがい)という言葉も、最近ではよく聞かれます。
(もちろん、精油に含まれる化学成分と同じ化学成分の香りの作用は同じと考えられるので精油(天然香料)だから香害がないということはいえません。)
精油の主な効果とは?初心者が知っておきたい魅力
▮香りによるリラックス効果
精油の香りを嗅いだとき、ふっと肩の力が抜けたように感じたことはありませんか?
香りが私たちに作用する中でも、最も速く反応が起こるのは「嗅覚」からの働きだといわれています。
香りの成分(芳香分子)は、鼻から取り込まれ、嗅覚受容器を通って「嗅球(きゅうきゅう)」へ届き、そこから電気信号として脳の「視床下部」へダイレクトに伝わります。
視床下部は、自律神経やホルモンバランスを調整するほか、心地よさや不快感、興奮や安らぎといった感情をつかさどる「大脳辺縁系」ともつながる、心と体の司令塔のような役割を持っています。
そのため、香りを嗅ぐことで脳や身体に生理的な変化が生まれ、リラックスを感じることがあるのです。
▮気分転換・集中力向上などのメンタルケアに
朝に清涼感のある香りを取り入れることで、交感神経が刺激され、気分がリフレッシュされたり、脳の覚醒レベルが高まり集中力が高まったりすることが知られています。
精油の香りは、自律神経や脳内の神経伝達物質に働きかけ、心身の状態に影響を与えるため、気分や目的に応じて選べるナチュラルで効果的なメンタルケアツールといえます。
<補足>
交感神経:活動や緊張のときに優位になる自律神経。
神経伝達物質:脳内で感情や覚醒、リラックスなどに関与する化学物質(例:ドーパミン、セロトニンなど)。
自律神経:体の無意識の働きを調整する神経で、交感神経と副交感神経がある。
▮お肌や空間ケアなど、暮らしへの応用
精油は香りを楽しむだけでなく、植物由来の有用成分を活かして、スキンケアや空間の抗菌・消臭など多目的に活用できる自然由来の機能性素材です。
一部の精油には抗菌・抗ウイルス・抗酸化作用が確認されており、手作りの化粧品やルームスプレー、ディフューザーなど、日常生活のさまざまなシーンで肌や空間の健やかさをサポートするアイテムとして取り入れられています。
合成香料と異なり、天然の芳香成分による心地よい香りと機能性が両立することから、ナチュラル志向の方々にも高く支持されています。
初心者におすすめの精油5選
1.オレンジスイート(Citrus sinensis):気分を明るく元気に
甘くて親しみやすい香り。子どもにも人気があり、初めてでも取り入れやすい精油です。日本人に最も好まれる香りともいえるかもしれません。
2.真正ラベンダー(Lavandula angustifolia):リラックスと万能感が魅力
初心者にまずおすすめしたい1本。心地よく眠りたいときや、緊張を和らげたいときに最適です。メーカーによっても香りが異なるので、嗅ぎ比べて好き!と感じるものを選ぶとよいと思います。
私個人的には、ラベンダーの香りはあまり好きではなかったのですが、ARTQ ORGANICS(アロマティークオーガニクス)の真正ラベンダー(Lavandula angustifolia)を嗅いだ時にこのラベンダーの香りは好きだなぁと感じました。
3.ユーカリプタスラディアータ(Eucalyptus radiata):呼吸器系のケアに
すっきりとした爽快な香りで「肺を開く・OPEN THE LUNG」という代名詞をもつほど呼吸器系への活用や有効性が説かれてきた精油です。
マスクスプレーや空間のリフレッシュ、風邪予防にもおすすめ。
4.ペパーミント(Mentha piperita):リフレッシュ・清涼感
頭をスッキリさせたいときにぴったり。夏場のクールダウンや、眠気覚ましにも活躍。(※小さい子供への使用や使用量などに注意が必要です。)
5.ヒノキ(Chamaecyparis obtusa):日本人に馴染みやすい森林の香り
森林浴のような癒しを与えてくれる香り。落ち着きたいときや、心を整えたいときに。
※()内は学名です。
精油の基本的な使い方
▮まずは簡単に「ティッシュや紙に垂らすだけ」
一番手軽なのは、ティッシュや紙に1~2滴垂らして、香りを楽しむ方法。
デスクや枕元に置くだけで、すぐに香りのある空間が作れます。
▮アロマストーンやディフューザーを使う
精油は熱に弱いので、火や熱を使わないものがおすすめです。
自然気化式のアロマストーンやウッドディフューザーは精油を垂らすだけで使えます。電気も必要ないので手軽です。
広範囲に拡散したい場合は、「水なしのネブライザー式」「超音波式」「ファンなどを用いた気化式」のアロマディフューザーを使うとよいです。
広範囲に拡散したい時に個人的におすすめなのは、水を一切使用せずに精油そのものを微粒子にして拡散させるネブライザー式のアロマディフューザーです。精油本来の香りが楽しめます。
初心者向けでおすすめなのは超音波式のアロマディフューザーです。水と精油を混ぜてミスト状に拡散する仕組みです。アロマが使用できる加湿器などで一般的に普及しているので使いやすいと思います。
また精油は熱(火)に弱いと書きましたが、引火する可能性がありますので火気まわりでの使用は避けてください。
▮お風呂やスプレーなど応用方法も少し紹介
お風呂に数滴垂らして香りを楽しむ「アロマバス」や、精製水と混ぜて作る「アロマスプレー」もおすすめです。
お風呂の床に垂らして、シャワーのお湯の蒸気で拡散させるのもよいです。
精油は油溶性なのでホホバ油などの植物性オイルに混ぜて溶かせば、マルチに使える「保湿オイル」も簡単に作れるのでおすすめです。
※肌に直接使う場合は、必ず希釈し(まずは1%以下を目安に)、パッチテストを行いましょう。
精油を選ぶときのポイントと注意点

▮学名を確認しましょう
精油は一般名と世界共通で使用される学名(ラテン名)を持っています。
一般名は各メーカーで命名しているので各社で異なりますが学名は共通の名称なので、学名を確認するようにしましょう。
▮「100%天然精油」と書かれているかをチェック
選ぶときは、ラベルに「100% pure essential oil」などと書かれているかを必ず確認しましょう。
(きちんとした品質のものでも書かれていないことはあります。)
オーガニック認証マークがついている精油を選ぶのも一つの手段です。
▮初心者は香りの好みで選ぶと◎
最初は「いい香り」と感じるものを選ぶのがコツ。香りの好みは人それぞれなので、まずは好きな香りから始めてOKです。
▮妊娠中・子ども・高齢者・ペットがいる場合の注意点も簡単に紹介
妊娠中や小さなお子さま、高齢者、ペットのいる家庭では、使用する精油や使い方に注意が必要です。
使用前に信頼できる情報を確認しましょう。
まとめ|精油は香りを楽しむ“自然からの贈り物”
精油は、香りの力で心と体にやさしく働きかけてくれる自然の恵みです。
まずはひとつ、自分の好きな香りを見つけるところから始めてみてください。
暮らしにそっとアロマを取り入れることで、気持ちの切り替えやリラックスの時間が、きっともっと豊かになるはずです。